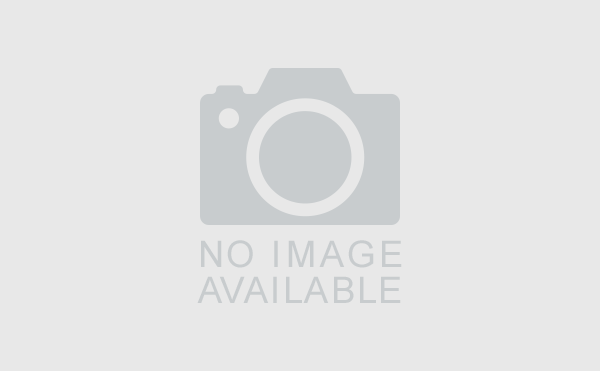法人設立初年度の役員報酬 ― 期の途中から支給しても大丈夫?
会社を設立したばかりの頃は、売上の見通しが立たず、「しばらくは無報酬で頑張ろう」と考える方も少なくありません。
しかし、法人税の計算上、役員報酬には厳格なルールがあり、支給のタイミングを誤ると、会社の経費(=損金)として認められない場合があります。
ここでは、設立初年度に注意すべき「役員報酬」の取り扱いについて、実務的な観点から整理していきます!
役員報酬を経費にするには「定期同額給与」であることが条件
法人税では、役員報酬を会社の経費(損金)にするためには、次のような「定期同額給与」の要件を満たす必要があります。
- 1か月ごとなど、一定の期間で定期的に支払われていること
- 毎回の支給額が同じであること(同額であること)
- 事業年度開始から3か月以内に設定された金額であること
つまり、「期の途中で報酬を支払い始めた」「途中で金額を変更した」などの場合、定期同額給与として認められず、損金に算入できない可能性があります。
設立から半年後に支給を始めるとどうなる?
たとえば、設立時に「売上が見通せないから当面は無報酬」と決めておき、半年後に報酬を支払い始めた場合を考えてみましょう。
このとき、税務上の判断は「新たに報酬を制定した」とみなされるのか、「ゼロから増額した=改定」とみなされるのかがポイントになります。
この点、税務通信3870号によると、多くの場合「改定」と判断されるのが一般的です。
そのため、役員報酬の支給を始めた時期が法人設立から3か月経過後である場合、損金にできないという扱いになります。
特別な事情がある場合は例外も
ただし、設立直後に営業を開始できないケース(たとえば許認可事業など)では、次のように考えられる場合もあります。
- 設立後すぐは営業活動が禁止されており、実質的な役員の活動がなかった
- 許認可を取得してから実際に事業をスタートした
このような場合には、許認可取得後に役員報酬を決めても「新たに制定した」と解釈される余地があります。
つまり、支給が期の途中であっても損金算入が認められる可能性がある、ということです。
ただし、この点は法令で明確に定められているわけではなく、実際には税務署や顧問税理士との慎重な検討が必要になります。
実務上のポイント
設立初年度の役員報酬を決める際には、次の点を意識しておくと安全です。
- 設立から3か月以内に役員報酬を設定する
→「事業年度開始から3か月以内に設定された金額」であることが損金算入の基本条件です。 - 一度決めたら、期の途中で変更しない
→変更は原則できません。どうしても変更が必要な場合は、職務変更や経営悪化など、要件を満たす必要があります。 - 議事録などの社内記録を整備しておく
→役員報酬の決定日・決定内容がわかるように、株主総会議事録や取締役会議事録を必ず保管しましょう。
まとめ
設立初年度は、事業が軌道に乗るまで不安定な時期ですが、役員報酬を安易に「後から決めよう」とすると、税務上の経費にできなくなるリスクがあります。
特に、社長自身の報酬については「支給時期」や「決定時期」を早めに明確化しておくことが重要です。
- 設立から3か月以内に報酬を決定
- 原則として期の途中の変更は不可
- 特殊事情がある場合は専門家に相談
役員報酬の設定は、税務だけでなく資金繰り・社会保険・個人の所得税にも影響します。
設立初年度こそ、慎重な設計が求められるポイントといえるでしょう。
「役員報酬をいくらに設定するか?」は設立時に大変悩まれる方が多いポイントです。
当事務所では、創業期の企業様向けに「役員報酬設計」「税務シミュレーション」などのサポートも行っておりますので、是非お気軽にお問い合わせください!
初回相談は無料です!